こんにちは。スバコミ事務局のみなさん。
なかなかバタついていて、お題を振られているインプレッサ555についての資料のスキャンや画像処理、テキストの作成などの時間が取れずに投稿が滞ってしまい申し訳ありません。もうお話ししたいことはとても語り尽くせないほどあって、早くお伝えしたくて悶え狂って死んでしまいそうなほどイライラしているのですが、まあ放っておいて無くなってしまうものではありませんから、スバルWRCチャレンジの時系列に沿って、あの栄光を汚さないように、あまりお見苦しくない読み物をお届けしたいと考えておりますので、もうしばらくお時間をください。
さて、これまでざっとではあるんですが、1990年のWRCチャレンジ開始から、1993年のインプレッサ555の1000湖ラリーデビューまでをお話しさせてもらいました。もちろんWRC1993年シーズンはこれでおしまいではなく、スバルにとっても、私たちスバリストにとっても、あまりにも悲しいラリーとなってしまった、プロドライブレガシィ最後のレースであるラリーオーストラリア、スバルイタリアとARTがP・リアッティのドライブでプロドライブレガシィで出場したサンレモ、そしてプロドライブのお膝元イギリスで開催されたRACラリーにインプレッサ555、そしてバーンズとアリスター・マクレーのイギリス選手権組のレガシィRSで戦っていて、それは翌年、カルロル・サインツとㇾプソルという新たな仲間とスポンサー、さらにピレリによる充実したタイヤサポート体制を迎え、WRC全戦に参戦する直前の、スバルがWRCのトップコンテンダーに上り詰めていく道程としてどうしてもお話ししなければならない事柄がたくさんあるのですが、今回はそこをぐっとこらえて、WRC参戦車両であるプロドライブレガシィ、そしてインプレッサ555のベースとなった、BC5型レガシィRS 、GC8型インプレッサWRX の違いについてお話しさせて頂きたいと思います。
「インプレッサWRXはレガシィRSのダウンサイジング版である。」という広く定着した見方はまったくその通りで、GC8型インプレッサWRXはBC5型レガシィRSより一回り小さくなって車両重量がより軽量になり、ホイールベースが短くなって操縦性が鋭くなり、ゆえにラリーフィールドにおける戦闘力が向上しました。そのあたりについてもう少し突っ込んでみましょう。

具体的に、ボディサイズで見ると、インプレッサWRXはレガシィRSと比較して、全幅は日本の5ナンバーサイズ一杯の1695㎜で同一ですが、全長で-170㎜、ホイールベースで-60㎜短縮されました。全長に比べてホイールベースの短縮比が少ないのは、当然操縦性をあまりシビアにしたくないという思惑からで、この数値は初代GC/GF型インプレッサ の開発段階からWRCの実働部隊であるプロドライブに意見を求めて最適な数値を模索したそうです。
車重は、レガシィRSが1280kg、インプレッサWRXが1170kg(いずれもタイプRA比)で、-110kgの軽量化となりましたが、これはあくまでも市販版での比較で、競技ベースとして重要となるボディモノコックの重量は、レガシィRSが約200kgであるのに対して、インプレッサWRXが170kgと、-30kgの軽量化を実現しました。当時のグループAラリーカーの最低重量は1100kgで、グループA仕様のプロドライブレガシィでも全備重量でこれを下回っており、最低重量との重量差は、慣性モーメントの低減(つまり「マスの集中化」)のために、バラストをリヤバルクヘッド(トランクルームと室内の隔壁)や後席足元に積むことで改善していました。インプレッサWRXでモノコック本体で30kgの軽量化を果たしたことで、より効果的なバラストによる重量調整が可能になり、このことが同じ車重ながら、インプレッサ555により鋭い操縦性と安定したトラクション性能による高い戦闘力をもたらしました。
パワートレインでは、EJ20G型であることに変わりはありませんが、インタークーラーをレガシィRSの水冷式からインプレッサWRXでは空冷式に変更。実はレガシィの水冷式インタークーラーでも吸気温度の上昇によるパワーダウンはあまりなかったのですが、一方でインタークーラー用ラジエター、ウォーターポンプ、リザーバタンクで構成されるシステム重量は約10kgで、これを空冷化することで7kgの軽量化を実現。また市販車にインタークーラーウォータースプレイを装備することで、グループA仕様でも10ps程度のパワーアップと高温のラリーや長距離のステージでも安定した吸気温度を保てるようになりました。
さらに、レガシィRSのバルブ駆動システムが、HLA(ハイドロリッククラッシュアジャスター)付のロッカーアームを介したものから、インプレッサWRXでは、カムが直接バルブを駆動するダイレクトプッシュ式に変更され、バルブ周りの慣性重量を低減して、高回転でも安定したバルブ追従性を実現するなど、インプレッサWRXにはWRCの頂点に立つために、レガシィRSで培った実にきめ細やかな変更が加えられています。
ではそうした変更が実戦でどのような効果を現したのか?ということを当然皆さんお知りになりたいと思うでしょう。それを知ることのできる貴重な動画があります。イタリア・ボローニャで開催されていた「ベッテガ・メモリアル」の動画で、ドライバーはいずれもコリン。レガシィRSは1991年、インプレッサ555は1993年の時のもので、対するドライバーは、当時、イタリア選手権のフォードのドライバーの実力者だったジャン・フランコ・クニコ。シエラRSコスワース4×4とエスコートRSコスワースとスバルとの操縦性の違いも興味深いところです。

MEMORIAL BETTEGA 1991

Memorial Bettega 1993 - Cunico vs Mc Rae 2
ポイントは立体交差を越えて軽くジャンプしながら、フロントに荷重が移しにくい体制から、フルブレーキングしながらステアリングを切り込んでターンインしてから、車の向きが変わるまでの早さで、さらにその先のクランクに向けてどれだけスロットルを早く全開にして立ち上がれるかというところです。もうまったくインプレッサ555が他を寄せ付けない速さであることは一目瞭然です。
この動画から私は、改めてレガシィRSからインプレッサWRX、そしてレガシィからインプレッサ555に移り変わる間にスバルとプロドライブの技術陣が注ぎ込んだ情熱の大きさと進化、その偉大さに触れる、インプレッサ555がWRCで世界の頂点を目指して生まれた生粋のサラブレッドであることを知りました。
そしてその血統は、現在の、つい先日ニュルブルクリンク北コースで4ドアセダン世界最速記録を樹立したWRX STI タイプRA NBRスペシャルや、GRC、アメリカラリー選手権を戦うWRX STIのラリーカーや全日本ラリー選手権を戦うマシン、あるいはSUPER GT、ニュルブルクリンク24時間レースのマシンに受け継がれ、こうした生粋のレーシングマシンにごく近い、WRX STI を長い時間をかけて紡いできたヒストリーやヘリテージを誇りつつ、リーズナブルな価格で買うことができ、日常の生活で愉しむことができるなんて、スバリストはなんて幸せなんだろうとつくづく感じてしまうのです。


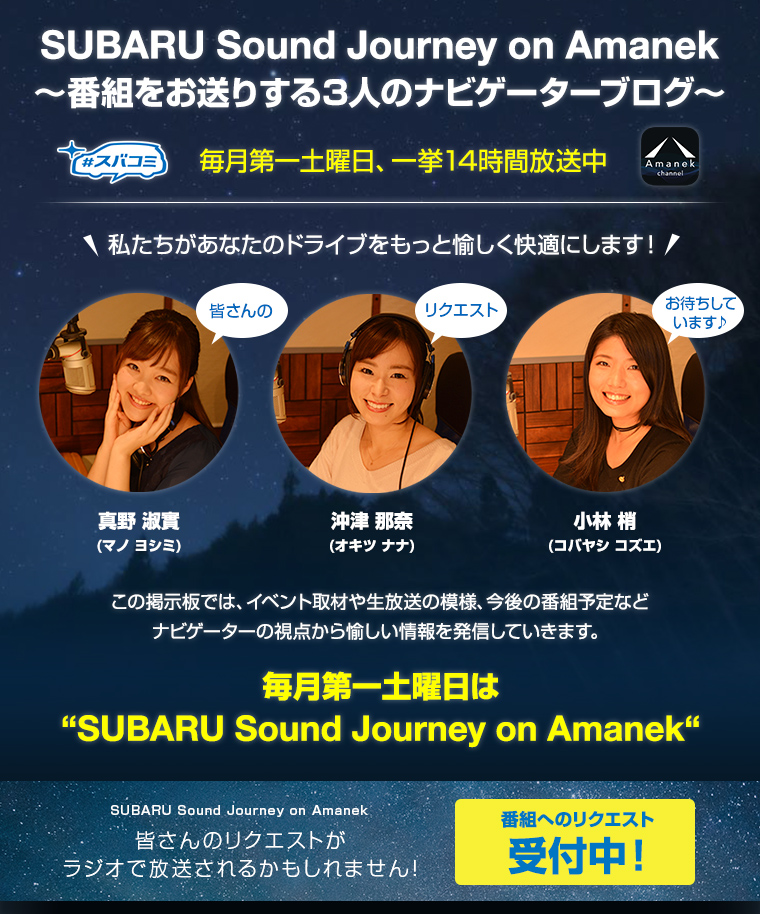

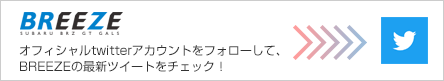
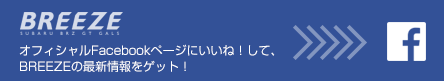


































_170413.jpg)







